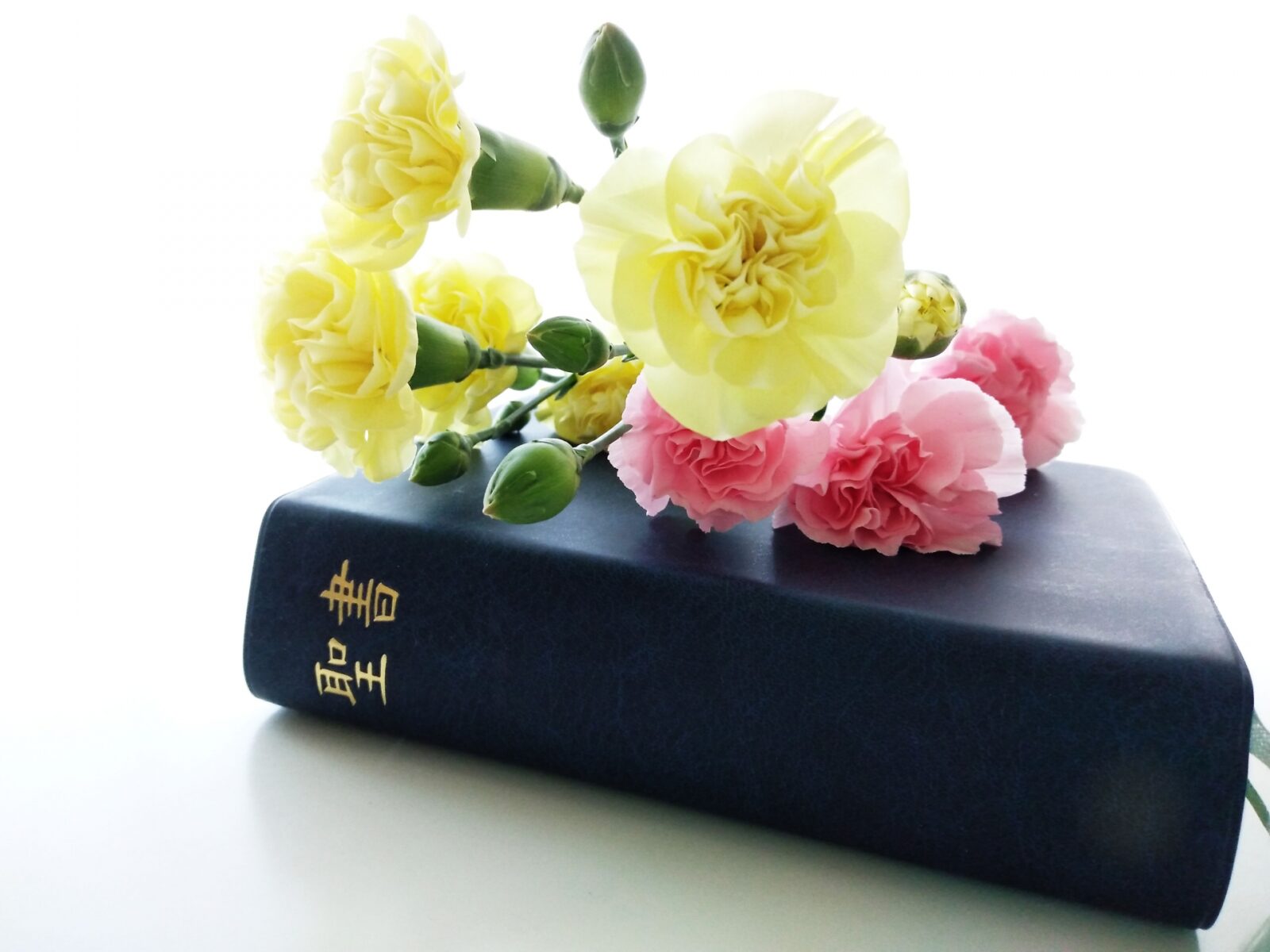神のみこころは、あなたがたが聖なる者となることです。…神が私たちを召されたのは、汚れたことを行わせるためではなく、聖さにあずからせるためです。テサロニケ人の手紙 第一 4章3、7節 (p411)
序 論) マタイの福音書5章の17節から後半は主イエスが旧約聖書の律法について語られたことが記されています。
17~26節は十戒の中の第六戒、「殺してはならない」(出エジプト記20章13節p135、申命記5章17節p324という戒めについて語られました。
主イエスはさらに他の律法について語られます。
今回の箇所を通して示されることは…
1.きよさと結婚について
主イエスは十戒の第七戒、「姦淫してはならない」という戒めについて語られます。(27-28) (出エジプト記20章14節p135、申命記5章18節p324)
ここでの「女」(28)の原語は「女」とも「妻」とも訳せる言葉です。(新共同訳では「他人の妻」と訳されている。)
ここでの「姦淫」とはすでに結婚している女性とみだらな関係を持つことです。
それは他の夫婦の誓約を犯す罪であり、自らの誓約に対する背信行為、裏切りとなります。
ここでの主のみことばは十戒の第十の戒めにも通じます。(出エジプト記20章17節p135)
第七戒を破ることは第十戒をも破ることになります。(ヤコブの手紙1章14-15節p458)
主は行為だけでなく心の中の罪を指摘されます。外形的にだけ律法を守ろうとしていた人たちには、これはまさに新しい教えでした。
「右目」や「右の手」についての命令は「誇張法」ですが、それほどに姦淫の罪は重く、つまずきの原因を取り除く必要があることを伝えようとしておられました。(27-28)
「ゲヘナ」(29-30)は永遠のさばきの場です。主がそれを繰り返して語っておられることは、ここでのみことばが、永遠のいのちに関わる厳粛な勧めであることを示しています。
31節は申命記24章1節(p356)の引用です。これは妻を保護するために定められていました。しかし、後には離婚状を与えさえすれば合法的に離婚出来ると受け止めるようになっていたのです。
しかし、主イエスは結婚の尊さを語られ、不貞(結婚後の性的な不品行)がない限り離婚すべきではないと言われます。(32) (マルコの福音書10章6-9節p87)
2. 神の御前での誓いの言葉
続いて主イエスは「誓い」について語られます。(33)
主はレビ記19章12節(p211)、民数記30章2節(p297)、申命記23章21-23節(p356)の言葉を要約して語られました。
これらの誓いについて律法学者たちは詭弁的な逃げ道を考案しました。
それは誓いを二種類に分け、神の名によるものは絶対に守るべきであるとし、神の名によらないものはその限りではないとしたことでした。
それで神ではなく「天」、「地」、「エルサレム」、「頭」を指して回避的に誓い、その誓いは破られてもよいとしました。
主イエスはこの誓いの偽善を指摘されます。(33-36)
「天」は「神の御座」、「地」は「神の足台」で神様の臨在を表しています。(34b-35a)
「エルサレム」は偉大な王、神ご自身のものです。(35b)
これらにかけた誓いも神ご自身と関わることであり、誓いに軽重の区別をつけることはできません。
そして、「髪の毛」だけでなく人の全存在が神様のものです。(36)
従って主イエスは、守ることのできないこと、守りたくないことなら「決して誓ってはいけません」と言われます。
そして、率直に事実だけを言うようにと語られました。 (37)
結 論)私たちは心の思い、言葉、行いにおいて様々な罪を犯してしまう者です。(マルコの福音書10章2-5節p87)
そのような私たち、すべての人のために主イエスは十字架で死なれ、復活されました。
主イエスの贖いによって私たちの罪は赦されました。
主を信じ、従う者のうちに、聖霊が与えられています。
神様は聖霊によって私たちを日々、きよめてくださいます。
神様は私たちが聖なる者となること、きよい歩みをすることを願っておられます。(テサロニケ人の手紙 第一 4章3-7節 p411)
私たちにとって一番大切なことは主イエスと共に歩むことです。そして、主によってきよめられることです。
日々、罪を主の御前に悔い改め、神様に立ち返りつつ、主と共に歩んでまいりましょう。
(参考)
マタイの福音書5章28節について
「女を見て色情を起こすは善きことでないのは勿論である。しかし、これ姦淫であるか。そのことが問題なのである。余はそうではないと思う。…
ルーテル(マルティン・ルター)が言うたことがある。『余は鳥が余の頭上を飛ぶことを防げることはできない。しかし余は彼をして余の頂(頭)に巣を作らしめない。』」
(内村鑑三『聖書の研究』「誤訳正解」より)(1861-1930)
「およそ男子たるもの、ただ一人の例外もなく、一人残らず姦淫罪をもってさばかれねばならない。」
(山本泰次郎 『聖書講義 マタイの福音書』より)(1900-1979)(内村鑑三の弟子)