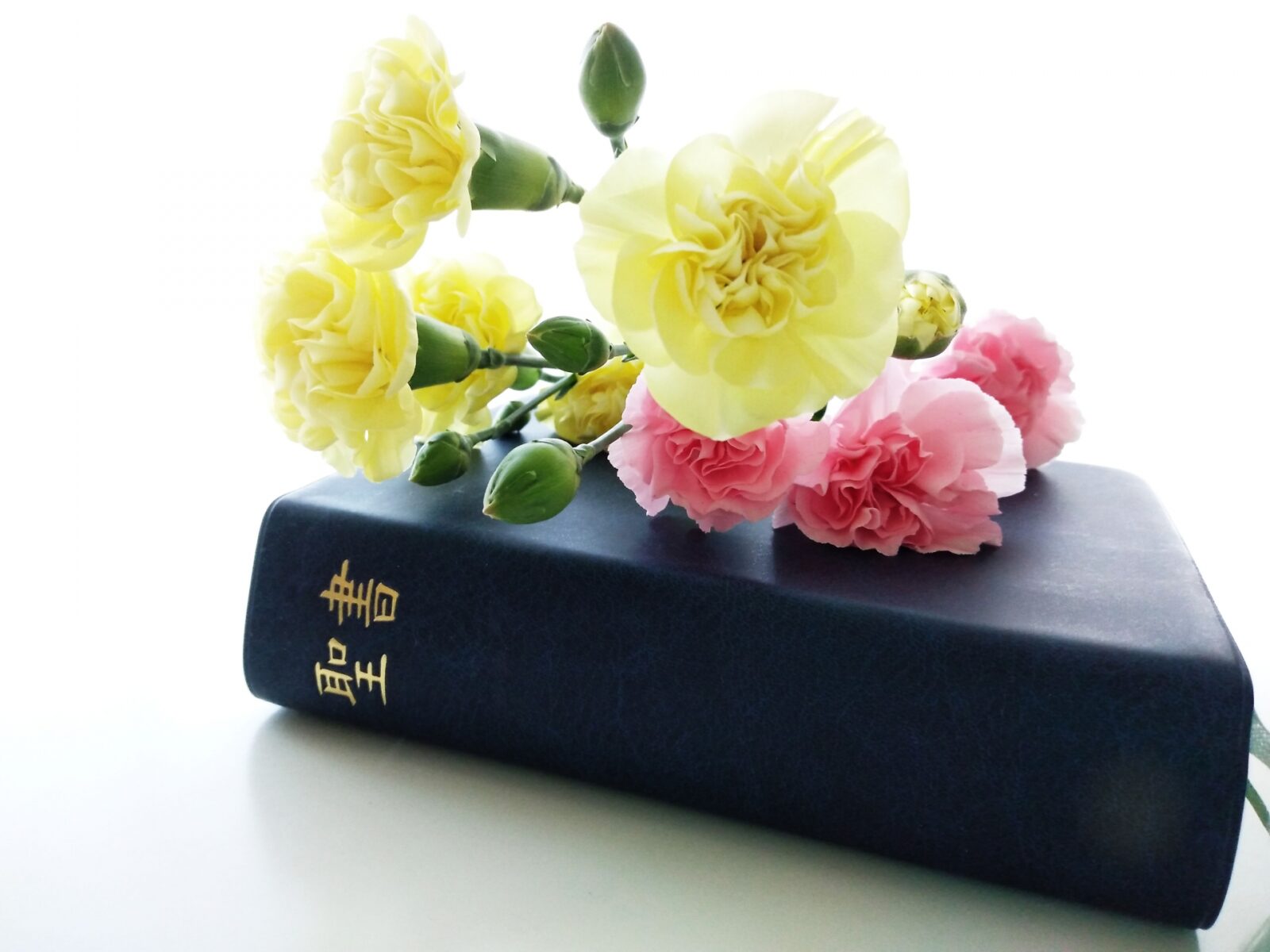三位一体・第7主日礼拝 2025.7.27
聖書箇所: マタイの福音書15章29―39節
説 教 題:「神をあがめ、感謝する」
説 教 者:辻林 和己師
そこで、イエスは群衆に地面に座るように命じられた。そして七つのパンと魚を取り、感謝の祈りをささげてからそれを裂き、弟子たちにお与えになったので、弟子たちは群衆に配った。 マタイの福音書15章35-36節 (p.32)
序 論)主イエスは弟子たちとツロとシドンの地方(フェニキア地方)を去り、ガリラヤ湖のほとりに行かれました。
そして、山に登られます。(29)
そこで起こった出来事と主の言行を通して示されることは…
1.異邦人の地での癒し
ここでの「ガリラヤ湖のほとり」(29)は、デカポリス地方(ガリラヤ湖の南東側)だったと考えられます。 (マルコの福音書7章31節p81)
そこは異邦人の地でした。
主イエスが「山に登り、そこに座っておられた」(29)のは、みことばを語られるためだったことでしょう。
ここでも、癒しを必要とする人たちが大勢、主のもとに連れて来られました。(30)
主はユダヤ人になされたように癒しの奇跡を彼らに対しても行われます。
主イエスは、カナン人の女性の娘を癒されたように、ここでも大勢の異邦人を癒されました。(28)
主の異邦人に対する恵みは「パン屑」だけでなく、もっと豊かなものであることを示されたのです。(15章26-27節)
主イエスが大勢の人たちを癒されるのを見た群衆は、驚きます。(31a)
そして、自分たちにあわれみを現わしてくださった、「イスラエルの神をあがめた」(31b)のです。
これは、癒された者の大部分の人たちが異邦人であることを示しています。
彼らは、ユダヤ人が信じているまことの神様をあがめました。
「あがめる」の原語には、「賛美する」、「神に栄光を帰する」という意味も含まれています。
2. 四千人に食べ物を与えられる
群衆は三日間も自分たちの家を離れて、主イエスのもとにいました。
主イエスは、彼らのことを心配され、ご自分から弟子たちに話を切り出されます。(32)(五千人が養われたとき(第一のパンの奇跡)のときは、弟子たちの方から言い出している。 (14章15節p29))
主のことばを聞いた弟子たちは、食物の乏しさを訴えました。(33)
しかし、そこにあったのは、七つのパンと少しの小さな干し魚だけでした。(34)
かつて第一のパンの奇跡のとき、人々は「草の上に」座りました。(14章19節p29)
そのときの季節は春であったことがわかります。
それから、約半年が過ぎ、このときの季節は夏の終わり頃で草は枯れていました。
主イエスは群衆に「地面に」座るよう命じられます。(35)
主はパンと魚を取り、父なる神様に感謝の祈りをささげてからそれを裂かれ、弟子たちに与えられました。(36)
彼らはそれらを群衆に配りました。
群衆の空腹は満たされたのです。
第一のパンの奇跡(五千人のパンの奇跡)に対し、この第二のパンの奇跡は「四千人のパンの奇跡」とも呼ばれています。(38)(14章13-23節p29)
その後、主イエスは弟子たちと「マガダン地方」に行かれました。(39)(ガリラヤ湖の西側だったのでは、と考えられている。)
結 論)「五千人のパンの奇跡」はユダヤ人に対して、「四千人のパンの奇跡」は異邦人に対してなされたみわざでした。
後日、主イエスは弟子たちにこれら二つの奇跡について、弟子たちに尋ねられます。(16章9-11節p33)
第一の奇跡のときは「十二のかご」であり、第二の奇跡のときは「七つのかご」でした。
「十二」はイスラエルの十二部族(全イスラエル)を、完全数とされる「七」は全世界を象徴する数だと言われています。
主イエスは、イスラエルの民だけでなく、すべての人の救いのために十字架で死なれ、復活されたのです。
神様は、今もすべての人が救われることを願い、一人ひとりに働きかけておられます。 (テモテへの手紙 第一2章4節p419)
たとえわずかなものであっても、主イエスの御手によって祝され、用いられるとき、それらを通して主の大きなみわざが現わされます。
それぞれの賜物を主の御手にささげ、礼拝や宣教のために用いさせていただきましょう。