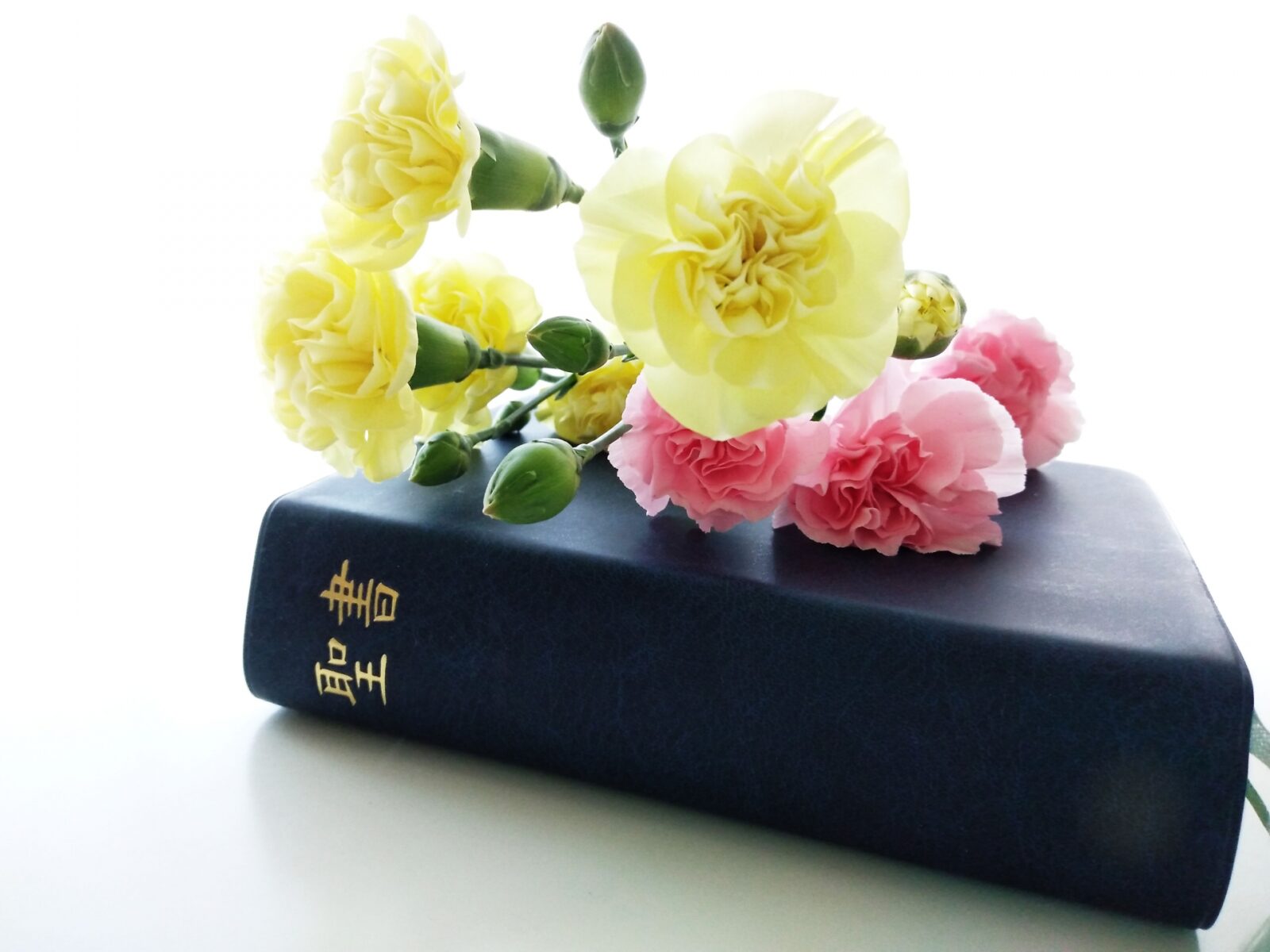「主よ。今こそあなたは、おことばどおり、しもべを安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの御救いを見たからです。あなたが万民の前に備えられた救いを。異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの栄光を。」 ルカ2章29-32節 (p.111)
序 論)救い主が誕生されて8日後、割礼が施され、イエスと名づけられました(21)。ヨセフとマリアは、エルサレムで幼子イエス様を主にささげるため(23)、神殿に向かいます。(レビ記12章8節 p.196) そこで、「正しい敬虔な人」(25)シメオンに出会います。彼は幼子を腕に抱き、神様をほめたたえました。彼の「賛歌」から示されることは…
本 論)
1.救い主にお出会い出来た喜びを歌う
シメオンは、神の言葉に支えられながら、イスラエルの慰められることを待ち望んでいました。また、神様が遣わされる救い主にお出会いするまでは、死ぬことはないと聖霊によって告げられていました。(26)。
29節を直訳すると「今、主(神様)よ、あなたはあなたのしもべをあなたの言葉に従い、平安の中に去らせようとしておられます(去らせつつあります)」となります。
「今こそ、主よ、あなたはこの僕をして、お言葉のとおり安からかに、この世に暇乞い(いとまごい)をさせてくださいます。」(塚本虎二訳)
この「去る」という言葉は死を意味しています。
「今こそあなたは、…去らせてくださいます」は、「このようにあなたの救いを見させていただいたからもういつ御国に移されてもいいです」、という意味が込められています。
「主よ、あなたは今、この僕を今の務め(救い主を待ち望む務め)から解き放ってくださる。」という意味だと解釈する人もいます。
後に、古代のギリシアの教会において、このシメオンの賛歌をもとに聖餐の祝いの中で歌う礼拝式文が作成されました。
改革者カルヴァン(1509-1564)は、ストラスブール(フランス領、ドイツとの国境に近い地域にある)のドイツ人教会で、聖餐の祝いのときにこのシメオンの賛歌を歌っていたことに学んで、この礼拝式文に取り入れました。
聖餐の式文に入れられたのは「私の目が今あなたの御救いを見たからです」(30)という言葉によるのではないかと言われています。
シメオンは、神殿の雑踏の中で、両親と幼子イエス様にお会いできました。自分の腕に抱いた幼子に救いを見ました。この幼子に、イスラエルの救い、すべての人の救いがかかっていたのです。
2.主イエスの十字架と復活を預言した
「異邦人を照す啓示の光」(32)と歌っているように、シメオンは自分たちを支配するローマの人たちの救いをも願いながら、生き続けてきたのかもしれません。また、この言葉は、やがて異邦人にも福音によって救われる道が開かれること、主イエスが全人類の救い主となられることを預言する言葉ともなっています。
またシメオンは、これから成される主のみわざを母マリアに告げます(34-35)。イスラエルの民がイエス様を受け入れず、十字架で死なれることは、悲しみの「剣」(35)となって、マリアの心を刺し貫くことになります。
「…イスラエルの多くの人が倒れたり立ち上がったりするために定められ…」(34)は、イスラエルの人たちにとって、救い主イエス様が、つまずきの石とも救いの礎石ともなることを示しています。
この言葉(34-35)についてあるドイツの牧師は「主イエスはただ審くためだけに来られたのではない。マリアの胸に剣が刺し貫かれるような、痛みを与えるためだけではない。マリアにもその子が甦ったという知らせを聞かせられる。」と語っています。
「立ち上がらせる」という言葉の原語は、「よみがえらせる」「復活させる」という意味が含まれています。シメオンは主イエスの十字架と復活を預言したのです。
結 論)シメオンの地上の生涯の終わりは、信仰者の地上の生涯の終わりを先取りしていると考えられていました。
一年の終わりにも、改革派の教会では、シメオンの賛歌が歌われているそうです。
シメオンのように、長い間、神に仕えてきた敬虔な信仰者アンナも幼子イエス様にお出会いし、「この幼子」が救い主であることを証ししました。(36-38)
シメオンが、幼子イエス様を腕に抱き、神様に感謝と賛美をささげたように、私たちも主からの平安と喜びをいただき、主を共に礼拝し、主の御名をさらに賛美し、証ししてまいりましょう。
一年間の主の恵みと御守りを覚え、新しい年の歩みのた めに祈り、備えてまいりましょう。