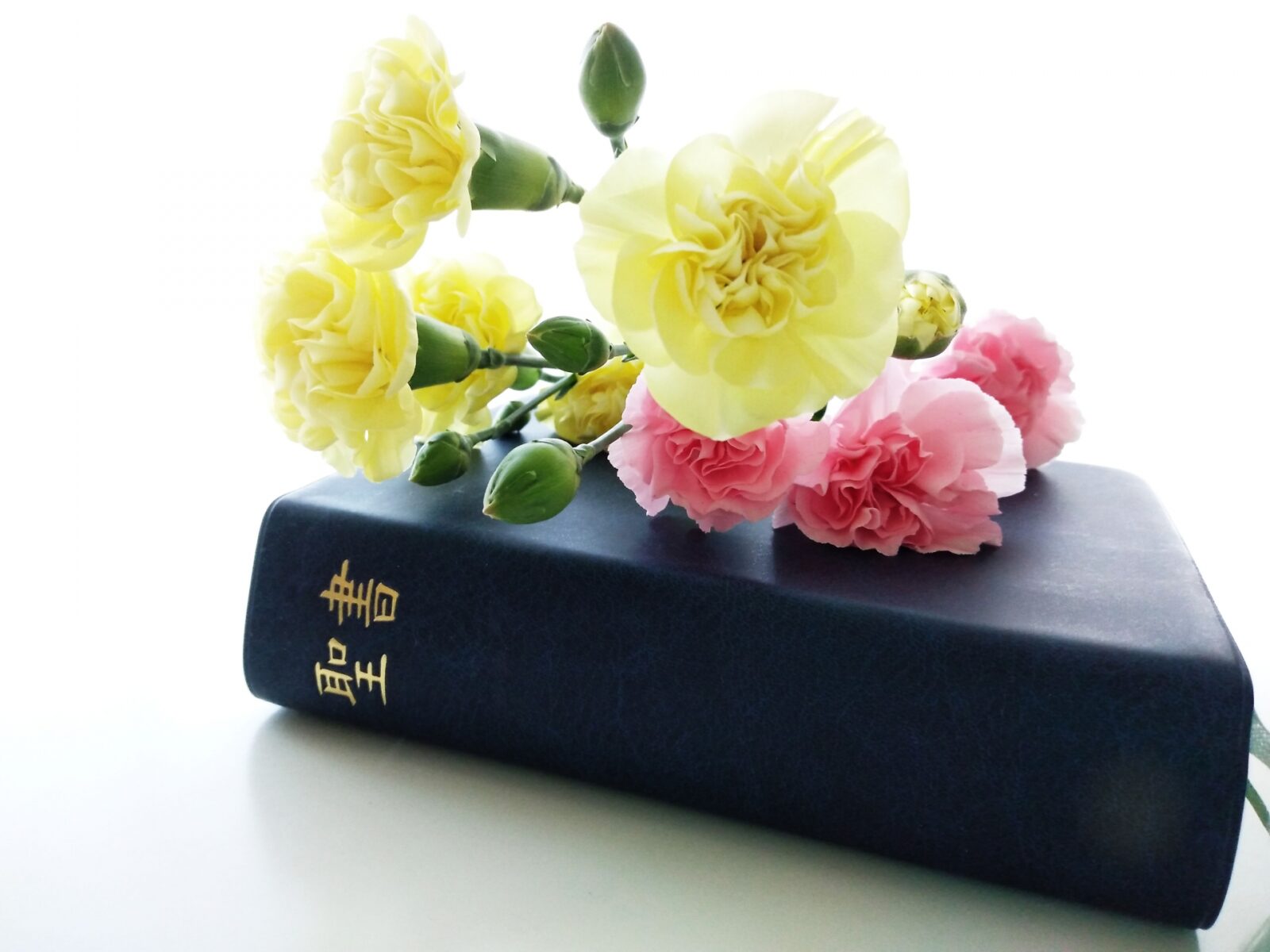ですから、あなたがたはこう祈りなさい。『天にいます私たちの父よ。御名が聖なるものとされますように。御国が来ますように。みこころが天で行われるように、地でも行われますように。…』 マタイの福音書6章9-10節 (p10)
序 論)主イエスは「山上の説教」の中で祈りについて語られます。(6章5-13節)
主はまず父なる神様と私との「一対一」の祈りについて教えてくださいました。(5-8)
続いて主イエスは弟子たちに「あなたがたがこう祈りなさい。…」(9)と祈りの言葉を教えてくださいました。
これは「主の祈り」と呼ばれています。
この祈りの言葉を通して示されることは…
本 論)
1.父なる神の御名が聖なるものとされますように
ここでの「御名」(9)は神ご自身のことを言われています。
「聖なるものとされますように」(9)は御名が他のものから区別され、聖とされますように、という意味です。
口語訳では「御名があがめられますように」と訳されています。 神の御名がほめたたえられますように、という意味です。これは神様を賛美する祈りでもあります。
「御国」(10)の原語は「神の国」とも訳される言葉です。これは「神のご支配」という意味です。
主イエスは「神の国は、あなたがたのただ中にあるのです。」と言われました。(ルカの福音書17章21節p153)
主イエスご自身の到来(地上に来られたこと)によって、 主を信じる者たちの内に「神の国」がもたらされました。(父なる神様との交わりが回復した。)
また「御国」は主の再臨によってもたらされる「神の国」 をも意味しています。「御国が来ますように」は神の国の完成を待ち望む、希望の祈りです。
「みこころ」(10)は、神様が願っておられること、ご計画のことです。
神様が私たちに願っておられることは私たちが「聖なる者となること」です。(テサロニケ人への手紙 第一 4章3節p411)
たちの日々の歩み(生き方)や選択が「聖(きよ)さ」につながることなのかを吟味する必要があります。
2.私たち自身の必要のために
イエスは「主の祈り」の後半で私たちの必要のために祈ることを教えられます。
日ごとの糧(かて)」(その日その日に必要なもの)(11)を求めることも神様が願っておられる祈りです。
ここで「私の」ではなく「私たちの…」と祈るように言われます。これは神の民がみな神様に養われ、支えられていること、神の栄光のために生きることを示しています。 (コリント人への手紙 第一 10章31節p342)
次は赦しを求める祈りです。ここでの「負い目」(12)は罪を意味しています。(口語訳では「負債」と訳されている)
イエスの十字架によって私たちの罪は赦されました。
しかし、私たちは罪赦されても、なお罪を犯してしまう者です。罪の赦しを続けていただくことが必要です。
罪赦された者は、人を赦す者とされます。ゆえになお自らの赦しを求めます。
次の祈りの中の「試み」(13)は、罪への誘惑です。「悪」は罪に誘う力であり、「悪い者」すなわち悪魔から来るものです。
神様が聖霊とみことばによって私たちに罪の誘惑に打ち勝つ力を与えてくださいます。
教会の礼拝の中で私たちがささげている「主の祈り」には最後に頌栄「国と力と栄えとは 限りなくなんじのものなればなり」が加えられています。
この頌栄は古代教会の時代に教会の礼拝で「主の祈り」がささげられるようになってから付加されたものです。
結 論) 「主の祈り」は短い祈りですが、「御名、御国、みこころ…」等、一つひとつの言葉に汲み尽くせない深い意味が込められている祈りです。
ある牧師は、毎朝の祈りの時、まず主の祈りを一言一言じっくり味わい、黙想しながら、神様にささげておられるそうです。
また「祈りの言葉が出てこない時は、主の祈りを神様にささげなさい」と別の牧師から教えていただいたこともありました。
父なる神様に共に祈れる恵み、主の祈りをささげることができる恵みを覚え、日々、祈りつつ歩みましょう。
(参考)
『聖書通読にチャレンジしよう!』(下川友也著)
『朝夕に祈る 主の祈り』(大嶋重德著)