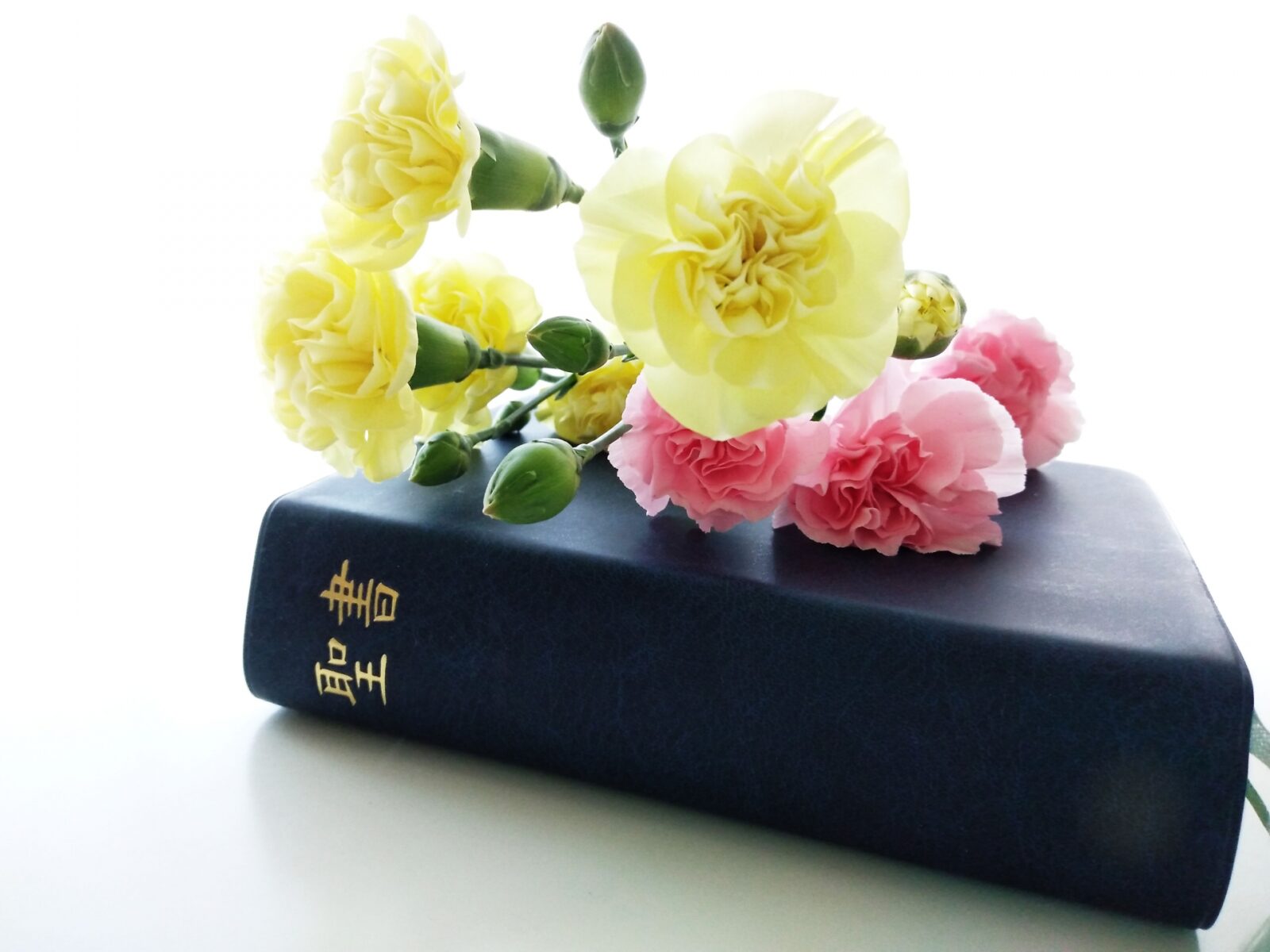そこでバルナバはサウロを捜しにタルソへ出かけて行き、 彼を見つけたうえ、アンテオケに連れて帰った。ふたりは、まる一年、ともどもに教会で集まりをし、大ぜいの人々を教えた。このアンテオケで初めて、弟子たちがクリスチャンと呼ばれるようになった。 使徒11章25-26節 (p.200)
序 論)ステパノの殉教により散らされた人々(使徒8章4節)は、ピニケ(パレスチナ北方の海岸地帯フェニキア)、クプロ(地中海の島キプロス)、アンテオケ(シリヤ州の首都)まで進んでいきました(19)。彼らの宣教の働きを通して起こった出来事とそれらを通して示されることは…
1 主の御手が彼らと共にあった
散らされた人々の多くが伝道の対象を「ユダヤ人」(19)だけにしていました。しかし、アンテオケに来た数人が、ギリシヤ人にも福音を伝えました(20)。
「イエスは主である」と宣教し、その結果、大ぜいの人たち(異邦人)が信じて主に立ち返りました。(21)
そのことを聞いたエルサレムの教会は、使徒バルナバをアンテオケに送ります。彼はキプロス出身のユダヤ人でした。(使徒4章36節 p.187)
彼は、多くの異邦人が救われた様子を見て「神のめぐみ」だと喜びました。(23) 彼は異邦人に古い律法の行いを強要したりすることなく、「主に対する信仰を揺るがない心でもちつづけるように」と皆を励ましました。(23)
主イエスを信じ、従うようになった人たちはここでは「主に加わる人々」と呼ばれています。(24)
多くの人たちが主を信じたのは、「主のみ手が彼らと共にあった」(21)からです。宣教の実りを生み出すのは私たちの力ではなく、主の御手です。主の御手のお働きは聖霊のお働きです。
私たちは、宣教のためにいろいろな計画を立て、それを実行していきますが、そのとき聖霊のお働きを求め、私たちの思いや計画を主の御手に委ねていくことが大切です。
主の御手が働いてくださるから、何の力もない小さな私たちを通して、主のみわざが成されていくのです。
2 エルサレム教会を支援する
その後、バルナバは宣教と信徒の教育のためにサウロ(パウロ)を彼の故郷タルソからアンテオケに連れてきました。(25-26) (使徒9章30節 p.196)
二人は協力し、一年間、宣教と教育に励みます。アンテオケでの弟子訓練(弟子教育)は実を結びました。(26)
キリストの弟子たちは主と教会に仕え、社会の中でも良い証しをし、影響を与えるようになっていきます。この弟子たちが「クリスチャン」(「キリスト者」新改訳、新共同訳)と呼ばれるようになりました。(26)
エルサレム教会とアンテオケ教会の交流が始まりました。エルサレムから預言者たちがアンテオケを訪れました。(27) その一人アガボが大飢饉が起こることを預言します。それが皇帝クラウデオの治世(AD41-54年)に起こりました。(28)
エルサレム教会の窮状を知ったアンテオケ教会は、経済的な支援を始めます。弟子たちは「それぞれの力に応じて」献げました。(29)
献金や援助の品をエルサレム教会のユダヤ人信徒たちに届けたのがバルナバとサウロでした。(30)
バルナバたちは、このことによってアンテオケの異邦人を中心とする教会とエルサレムのユダヤ人教会との間に互いに助け合い、支え合う良い関係が築かれることを願っていました。
この後、パウロは「異邦人の使徒」、異邦人に福音を伝える宣教者となっていきます。
結 論)このアンテオケで、キリスト信徒たちが初めて「クリスチャン」と呼ばれるようになりました。
「クリスチャン」という言葉は英語をそのまま訳した言葉です。「キリスト者」は、日本語的な表現だと言われています。
これはもともとはアンテオケの人々が、教会に連なる信徒たちのことを呼んだあだ名でした。
元のギリシヤ語の「クリスティアノス」は、「キリストのものである人、キリストに属する者」という意味です。
当時、教会の人たちは、口を開けばいつも「キリスト、キリスト」と言っていたことでしょう。「イエスこそ主であり、キリスト(救い主)である」「キリストは十字架にかかられ、復活された」と語り続けたのです。
教会は、主イエスをキリストと信じ、従うキリスト者が生まれるところです、そしてキリスト者が共に集い、留まるところです。そこで、主にある真実の喜び、励ましと慰めが与えられるのです。
イエス・キリストによる罪の赦しの恵みを受け取り、キリストに結ばれ、主イエスの御名を崇めて歩み続けましょう。