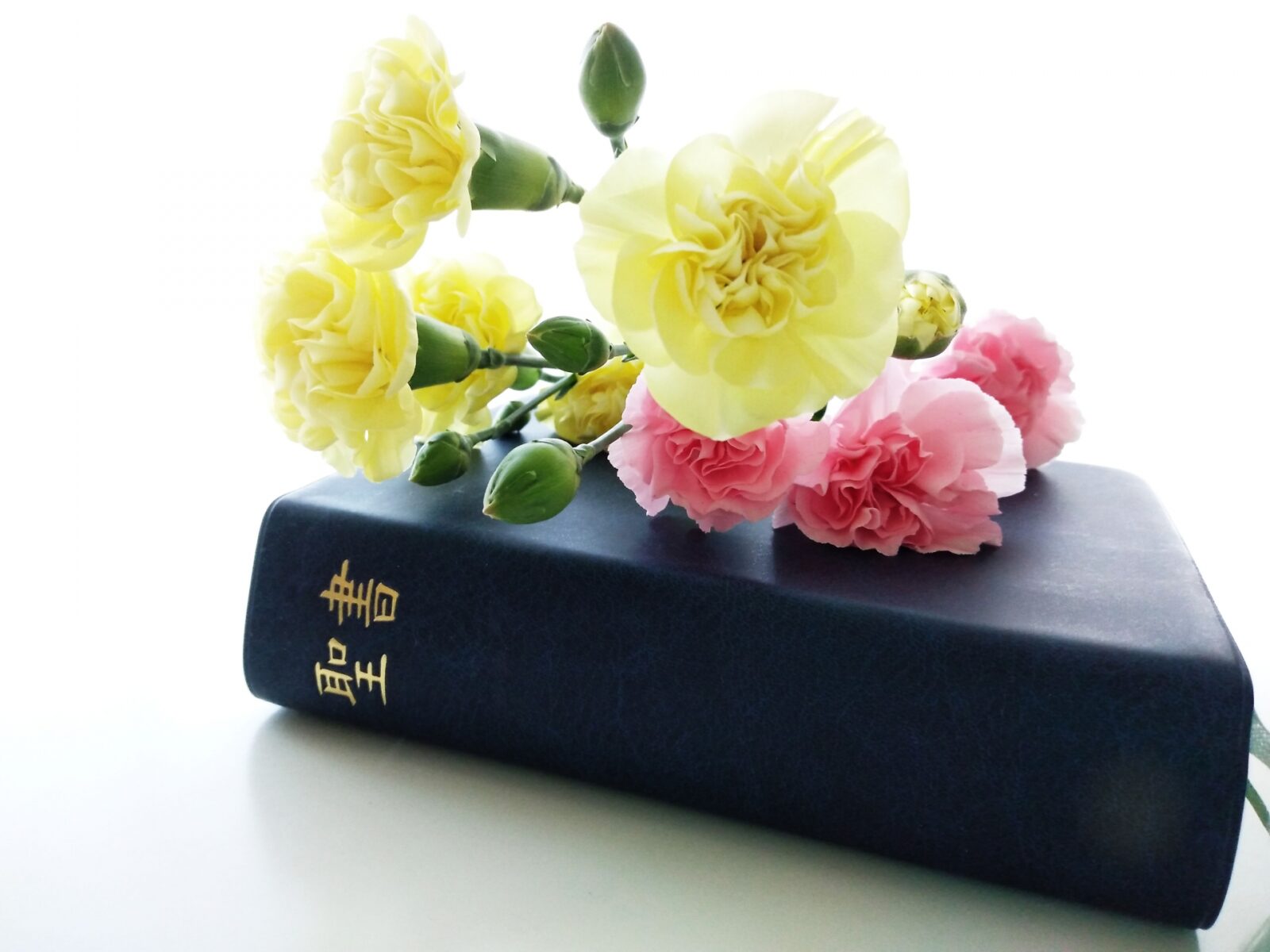ペテロが彼に言った、「アイネヤよ、イエス・キリストがあなたをいやして下さるのだ。起きなさい。そして床を取りあげなさい」。すると、彼はただちに起きあがった。 ルダとサロンに住む人たちは、みなそれを見て、主に帰依した。
使徒行伝9章34-35節 (p.196)
序 論)エルサレム教会への激しい迫害により、信徒たちは各地に散らされ、使徒たちはエルサレムに残り、教会を維持していました。(使徒8章2節後半p.193) その後、使徒ペテロもエルサレムを出て町々を巡回していました。(32) そして、彼は、二つの場所で、いやしと奇跡のわざをします。これらの出来事から示されることは…
1. イエス・キリストの名によってなす
「ルダ」(32)は、エルサレムからヨッパに至る途中にある町です。(聖書巻末の「キリスト時代のパレスチナ」参照) その地にアイネヤという名の信徒がいました(33)。彼は、中風を患っていました。8年間、寝たきりでした。
ペテロは、彼に声をかけます。(34) ペテロは主イエスの御名によって、彼をいやしました。
主イエスは十字架にかかられ、三日目に復活されて、その後、天に上げられました。もう、主は地上にはおられません。しかし、主イエスが地上におられたときになされたことと同じような奇跡のみわざが起こりました。 (ルカによる福音書5章17-26節 p.196 等)
このことによって、主イエスが聖霊によって今も生きて働いておられることが示されたのです。
「起きなさい。」(「立ち上がりなさい」新改訳)(34) と言われ、ア
ルダとサロンに住む人たちは、それを見て、主に帰依しました。(35)
2.主イエスと共に立ち上がり、歩き続ける
「ヨッパ」(32)は、エルサレムから北西方向の港町です。 そこには、伝道者ピリポの働きにより、キリスト者の群れができていました。(使徒8章40節 p.195)
女弟子タビタ(ギリシヤ語名はドルカス)は、ヨッパのキリスト者の群れにとって、よい働きをしていた人でした(36)。ところが、病気のため死んでしまったのです(37)。
教会の人たちは、ペテロがルダにいることを知って、急いでヨッパに迎えました。(38-39a) ペテロに皆を慰めていただこうと願ったことでしょう。
これまでタビタの世話を受けていたやもめたちは嘆きます。タビタは彼女たちに多くの施しや慈善をしたのです(39b)。
ペテロは、皆の者を外に出し、ひざまずいて祈ります。 そして、タビタに呼びかけました。(40) すると、タビタは生き返り、起きなおりました。
かつて主イエスは、死んでしまった少女を生き返らせられました。(マルコ5章35-43節 p.59)
「タリタ、クミ」(「少女よ、起きなさい」)
ペテロは師である主イエスにならうことにより、この群れの悲しみをいやそうとしました。タビタに声をかけたのはペテロですが、いやしのみわざをなしたのは聖霊の力でした。
タビタは主と共に新たな人生を歩き始めました。さらに喜びをもって主と教会に仕えたことでしょう。
タビタのよみがえりを知ったヨッパの多くの人たちが、 主イエスを信じました。(42)
結 論) 「起きる」(34, 40)の原語には「よみがえる、 復活する」という意味も含まれています。
十字架にかかられ、復活されたイエス様を救い主と信じ、 受け入れた者は、イエス様と共に死に、共に復活させられた者です。そして、新しい命に生かされた者です。
私たちは、困難や苦しみの中にあっても、主イエスと共に新たに立ち上がることがでます。そして、主からいただいたご愛と慰めを周りの人たちに分け与えることができる のです。
「主に帰依した」(35)は、「主に立ち返った」(新改訳) 「主に立ち帰った」(新共同訳)とも訳されています。
主に立ち帰るとは、主イエスに心を向けることであり、 主イエスを信じることです。(42)
神様は、私たちに主イエスに心を向け、信じることができるように日々、働きかけておられます。
私たちは、主イエスに立ち帰った者であり、日々、キリストに向かって造り変えられ、成熟している者です。 その恵みを覚え、日々、主との交わりによって新たにされ、 歩み続けてまいりましょう。