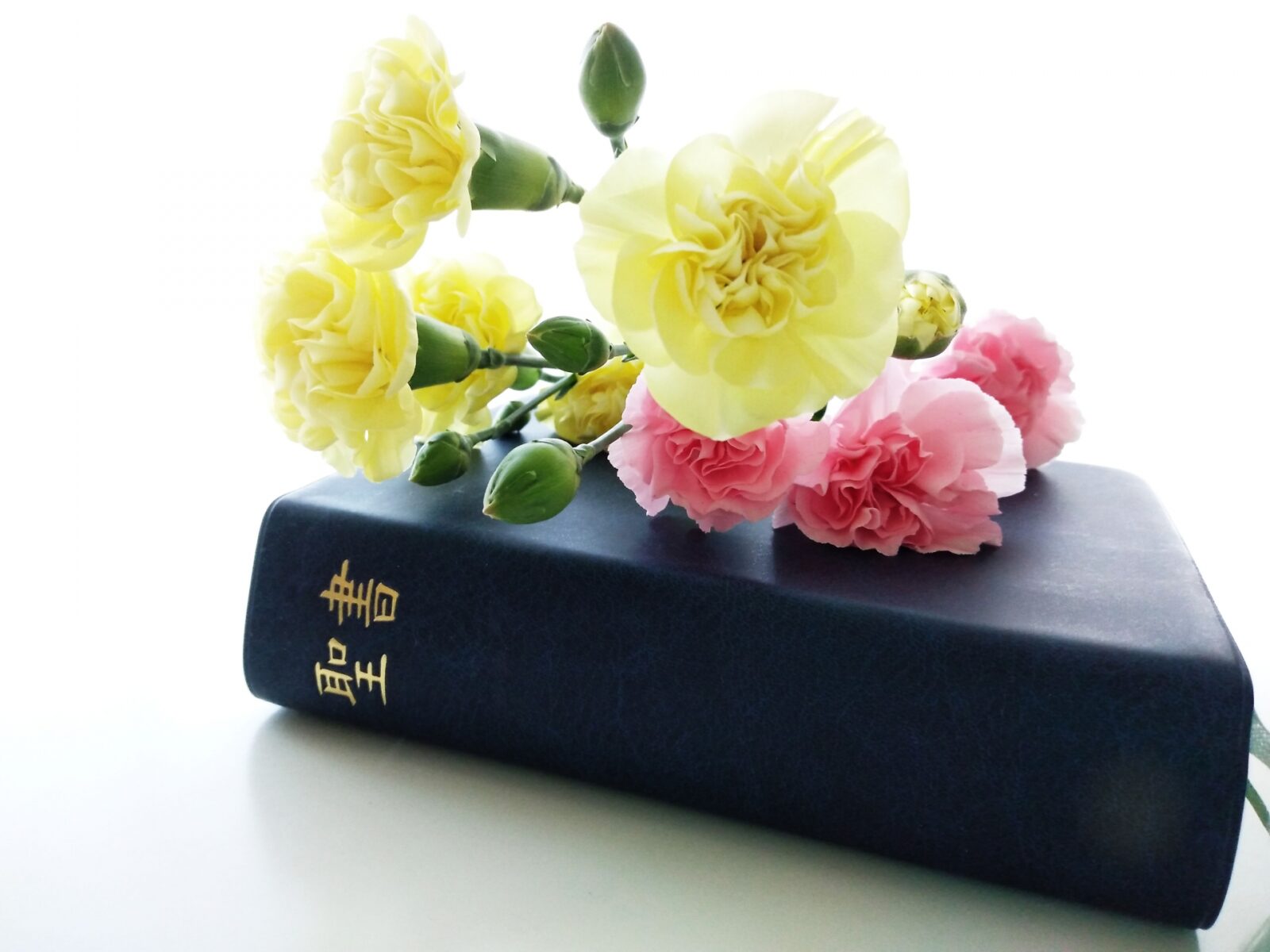こうして教会は、ユダヤ、ガリラヤ、サマリヤ全地方にわたって平安を保ち、基礎がかたまり、主をおそれ聖霊にはげまされて歩み、次第に信徒の数を増して行った。 使徒9章31節 (p.196)
序 論)キリスト者を迫害するために、ダマスコに向かっていたサウロ(後のパウロ)は、その途中、天からの光に照らされ(3)、主イエスの御声を聞きます。(4)
それまでの行いを悔い改め、イエス様を神の御子、キリスト(救い主)と信じたサウロの人生は180度、変えられました。
その後のサウロの歩みやバルナバたちの行いを通して示されることは…
1. 宣教と黙想
サウロはユダヤ人の集う諸会堂(シナゴーグ)で、イエス様が神の子であると宣べ伝えました。(20) その様子を見て、会堂の人々は驚きます(21)。
しかし、サウロは「ますます力が加わり」、イエス様がキリストであることを証ししました。(22)
その後「相当の日数」(23)の期間、サウロがどこで何を していたのかということに関しては諸説ありますが、当時、 「アラビヤ」と呼ばれていた「ナバテア王国」(現在のヨルダン西部)で3年間、過ごしたと考えられています。(ガラテヤ人への手紙1章17-18節 p.294)
そこでの期間は、サウロにとって、ひとりで神様の御前出て祈り、旧約聖書を読み直し、み言葉を黙想し、主イエスのとの交わりを持つときとなったことでしょう。 そして、この期間は後にローマ人への手紙、ガラテヤ人への手紙等で語られる「キリストの福音」をはっきりと示されるときともなりました。
私たちにとっても、信仰が強められ、霊的に成長するために、旧約、新約聖書を読み、み言葉を黙想し、神様に祈り、主イエスとの交わりを持つことが必要です。
日々聖書を読み、祈りを積み重ねる中で、神様の私に対 する願いが示され、キリストに従う者とされていくのです。
2.教会の交わりの中で育てられる
福音を語るサウロに、ユダヤ人たちは激怒し、彼を殺害しようとします。しかし、彼の弟子たちによって町の城壁づたいに、かごでつり降ろされ、危機から脱出したこともありました。(23-25) (Ⅱコリント11章32-33節 p.290)
その後、サウロはエルサレムに行き、弟子たちの仲間に入ろうとします。しかし、彼に対する疑惑や恐れはまだ消えてはいませんでした。(26)
そのようなとき、サウロと弟子たち、両者の仲立ちをしたのが、バルナバでした(27)。バルナバという名前は、「慰めの子」という意味です。(使徒4章36節 p.186) 「慰め」という言葉の原語は、「そばで語る」という語が元になっています。また「励まし」という意味もあります。バルナバはそのように教会の人たちにとって慰め、励ましとなる人でした。
バルナバは、弟子たちに、サウロの回心が真実であること、主イエスから伝道者として召命をいただいていること、伝道の働きが実を結んでいること等を説明しました(28)。
バルナバの仲立ちにより、サウロは使徒たちに迎え入れられ、エルサレム教会の働きにも参加しました。しかし、ここでも「ギリシヤ語を使うユダヤ人」(29)から命を狙われました。
そこで、エルサレム教会の弟子たちは彼を故郷のタルソに送りました。(31) 神様がサウロのために、バルナバを備えられたように、私たちも互いに「慰めの子」となることが願われています。
そして、サウロもそうであったように、私たちも教会の互いの交わりの中で、霊的に育てられるのです。
結 論)迫害のため、エルサレムから散らされて行った人たちは各地で宣教し、その中でサウロの回心の出来事が起こりました。それらの結果、教会がユダヤ、ガリラヤ、サマリヤの全地方に広がっていきました(31)
「基礎がかたまり」(「基礎が固まって」新共同訳)という言葉は、「家を建てる」という意味があります。教会が信仰においても、信徒の数においても、しっかりと建て上げられていったことが示されています。
当時、ユダヤとサマリヤ、ユダヤとガリラヤの間には歴史的に根深い対立がありましたが、教会はユダヤの境を超えてなお、「平安」が保たれていました。それは、ユダヤ、サマリヤ、ガリラヤそれぞれの教会が主イエスの十字架によるご愛と赦しをいただいていたからでした。彼らは民族間の対立や教会の様々な違いを乗り越えて、互いに祈り合い、赦し合いながら歩んでいったのです。
彼らは、「主を畏れ」、「聖霊に励まされて」歩みました。(31) 私たちも、主を畏れ、聖霊の慰めと励ましをいただき、互いに祈り、慰め、励まし合いながら、キリストの福音を 証ししてまいりましょう。